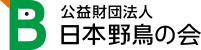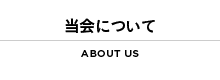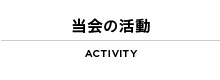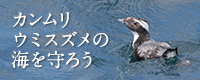- 日本野鳥の会
- 当会について
- 事業報告・決算等
- 事業計画・予算/事業報告・決算
- 事業報告2024(令和6)年度
事業報告2024(令和6)年度
2024年3月11日、日本野鳥の会は創立90周年を迎えました。
皆さまのご支援のもと、野鳥と人が共に生きる社会を目指して、1世紀弱にわたって自然保護に取り組み続けています。新たにスタートした90周年記念事業をはじめ、2024年度の活動をご報告します。
このコンテンツの内容は、以下のPDFファイルでもご覧いただけます。
※『野鳥』誌2025年7・8月号より抜粋
会長挨拶
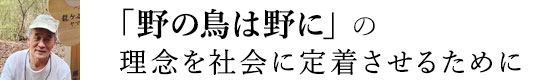
日本野鳥の会(以下、当会)は創立90周年を迎えました。日本で最も歴史のある、そしていまや国内最大の自然保護NGOです。会が創立されたのは昭和9年、それ以来90年間、当会は日本の自然と野鳥の保護に取り組んできました。
たとえば、絶滅が危惧されている北海道のシマフクロウやタンチョウの保護活動では、生息地の買い上げによる独自の野鳥保護区の設置やシマフクロウの巣箱かけ、タンチョウの生息環境の整備などです。
私たちが保護に取り組んでいるのはシマフクロウやタンチョウだけではありません。これらの鳥以外は北海道ではシマアオジとチュウヒそしてサンカノゴイ、伊豆諸島ではアカコッコとカンムリウミスズメを対象に、サンクチュアリのレンジャーと地元の連携団体が参加、協力して、地元自治体や住民と一緒に保護活動を繰り広げています。世間ではほとんど注目されていない鳥たちも、種類によっては個体数を減らし、絶滅の危険を抱えているのです。
海洋プラスチックの問題
当会が現在、重点的に取り組んでいるのは海洋プラスチックの問題です。海洋に漂うペットボトルやポリ袋、浮きや網といったプラスチック製の廃棄漁具などが、アホウドリやウミガメなどにからまることや、誤食の問題を抱えていますが、さらに深刻なのはマイクロプラスチックなのです。紫外線などで劣化して、どんどん細かくなり、プランクトンと一緒に海洋生物が体内に取り込んでしまっています。この問題は一朝一夕で解決はできませんが、拡大生産者責任の徹底などの法改正も含めて国レベルでの解決を求めています。身近なくらしで使い捨てプラスチック製品をなるべく使わない、探鳥会に合わせてごみ拾いをするなどの活動からも、この問題を多くの人に知ってもらうことが大切だと感じています。
生きものと共生できる風発を!

勇払原野で地元紙に
取材を受ける上田会長
当会は原発にかわる自然エネルギーの導入・推進に賛成しています。では自然エネルギーのための風力発電はどうなのかという問題が出てきます。私たちは風力発電すべてに反対という立場はとっていません。ワシ類やハクチョウ・ガン類、夜間に渡る小鳥類などの、頻繁な衝突が予測される地点に設置される風力発電施設には反対するという立場です。
4月に、当会のウトナイ湖サンクチュアリ(北海道苫小牧市)に行ってきました。サンクチュアリのレンジャーたちとの交流と、ウトナイ湖を囲むタンチョウやチュウヒが生息する勇払原野に計画されている風力発電施設について、現地の保護団体の方々からの意見聴取と現地視察が目的でした。
風力発電施設の建設が計画されているのは勇払原野の東側にある厚真町浜厚真地区です。ここはウトナイ湖サンクチュアリに近接し、自然度の高い湿原、草原、湖沼等がまとまって存在し、多数の希少動植物が生息・生育しているエリアです。雪が溶け、枯れたヨシが一面に広がっている早春の勇払の湿原には、真っ黒になった夏羽のノビタキのオスたちがあちこちにとまっていて、その上をチュウヒが悠然と滑空していました。オオジシギは到着したばかりのようで、盛んにディスプレイフライトを繰り返していました。最大6羽ものオオジシギが「ズビーヤク、ズビーヤク」と鳴きながら空中でもつれあっているのは圧巻の光景でした。海沿いに出ると、2羽のオジロワシが悠然と舞ってくれました。ビーヤク、ズビーヤク」と鳴きながら空中でもつれあっているのは圧巻の光景でした。海沿いに出ると、2羽のオジロワシが悠然と舞ってくれました。
この湿原ではタンチョウの繁殖も確認されています。2017年に最初のつがいが営巣してヒナを育て、それ以降、定着して繁殖を繰り返しています。これを地元むかわ町の「ネイチャー研究会inむかわ」や当会の苫小牧支部、一般社団法人タンチョウ研究所、ウトナイ湖サンクチュアリのレンジャーたちがずっと見守っています。
もしここに風力発電施設が建設されたら、この地域の生態系や生物多様性に大きな影響をおよぼすことが予想されます。現在、この事業は環境大臣や北海道知事、関連市町の首長、地元住民からの厳しい意見を受け、事業者は当初計画の10基のうち、タンチョウやチュウヒが営巣する海沿いに設置が計画されていた5基の建設を断念しました。しかし風車の数の削減によって、希少鳥類の生息環境の消失やワシ類およびガン類の渡りへの影響の懸念が、払拭されたわけではありません。残る5基の周辺にも同様の環境が広がっていることから、とくにチュウヒやワシ類の衝突の危険が予測されます。海沿いの5基だけでなく、残り5基についても、影響がないように中止を含めた建設計画の再考を求めるとともに、関係機関に対して当該地域における希少鳥類の生息環境保全を訴えていきたいと思っています。この湿原ではタンチョウの繁殖も確認されています。2017年に最初のつがいが営巣してヒナを育て、それ以降、定着して
繁殖を繰り返しています。これを地元むかわ町の「ネイチャー研究会inむかわ」や当会の苫小牧支部、一般社団法人タンチョウ研究所、ウトナイ湖サンクチュアリのレンジャーたちがずっと見守っています。
もしここに風力発電施設が建設されたら、この地域の生態系や生物多様性に大きな影響をおよぼすことが予想されます。現在、この事業は環境大臣や北海道知事、関連市町の首長、地元住民からの厳しい意見を受け、事業者は当初計画の10基のうち、タンチョウやチュウヒが営巣する海沿いに設置が計画されていた5基の建設を断念しました。
しかし風車の数の削減によって、希少鳥類の生息環境の消失やワシ類およびガン類の渡りへの影響の懸念が、払拭されたわけではありません。残る5基の周辺にも同様の環境が広がっていることから、とくにチュウヒやワシ類の衝突の危険が予測されます。
海沿いの5基だけでなく、残り5基についても、影響がないように中止を含めた建設計画の再考を求めるとともに、関係機関に対して当該地域における希少鳥類の生息環境保全を訴えていきたいと思っています。
私たちの理念
地域で探鳥会を開催し、さまざまなイベントを企画し、「野の鳥は野に」という私たちの理念を社会に定着させるために、全国の連携団体の皆さんが日々奮闘しておられます。いつも思うことですが、こうした全国津々浦々における皆さんの活動が、私たち日本野鳥の会の力の源泉になっています。現在までに紆余曲折はありましたが、私は当会の90年という歴史は重いと思っています。そして私たちに負わされた責任は大きいと考えています。
鳥たちに優しい社会は、人にも優しい社会です。野鳥を保護することは、この国の豊かな自然を保護することにつながります。さらにそれは自然界の一員でもある人間の健全なくらしを守ることにつながります。未来の子供たちのために、新たな活動に踏み出していきましょう。
日本野鳥の会会長 上田恵介

1950年大阪府生まれ。理学博士。動物生態学者。立教大学名誉教授。鳥類を中心とした動植物全般の進化生態学、行動生態学を専門とするかたわら、環境問題の研究にも取り組む。野鳥や自然に関する一般書の執筆、テレビ・ラジオ出演では、柔らかく、わかりやすい解説に定評がある。1963年の小学生の頃から、日本野鳥の会会員。2015年6月に日本野鳥の会副会長に就任。2019年6月より会長に就任