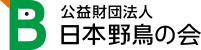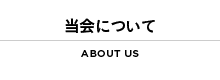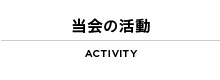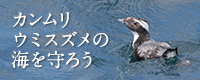バードアイランド三宅島の自然を守れ

三宅島・雄山の風景。2000年噴火で失われた緑は徐々に回復が進んでいる(写真:沖山勝彦)
今から25年前の2000年夏――三宅島で近年例のない大噴火が発生しました。
「バードアイランド」と呼ばれた野鳥と深緑の島に巨大な噴煙が立ち昇り、大量の火山ガスが流出。島に住むすべての人々が島外への避難を余儀なくされ、森の木々は立ち枯れて、人も野鳥も拠り所を失いました。
避難が解除された2005年、復興をめざし島に戻った日本野鳥の会のレンジャーたちは、噴火で激変した自然環境と向き合い、島の人々と協力し、自然と共生する新しいバードアイランドのあり方を模索してきました。あれから20年、今もなお、その挑戦は続いています。
島の人たちとめざす、自然とともに生きる未来
世界でも有数の火山島で自然豊かな三宅島はバードアイランドと呼ばれ、絶滅危惧種のアカコッコやカンムリウミスズメ、また伊豆諸島固有種が数多く生息する野鳥の宝庫です。

アカコッコ(絶滅危惧ⅠB類)
伊豆諸島やトカラ列島などに分布が限られているツグミ科の鳥で日本固有種。
国の天然記念物、絶滅危惧種にも指定されている
当会は、開発計画でゆれていたこの島の自然保護を1980年代から訴え続け、自然を活かす英断をした三宅村は1993年に「三宅島自然ふれあいセンター・アカコッコ館」を開設。運営を託された当会は、レンジャーを常駐させ、活動を続けてきました。
ところが2000年の大噴火で状況は一変。大量の火山ガスにより森の約6割が消失し、4年半を経て帰島が実現してからは、火山の影響の中での復興が大きな課題となりました。

噴火した直後のようす(写真:青谷知己)
全島避難の発令により、この噴火による人的被害はなかった
島に戻ったレンジャーは、「三宅型エコツーリズム」を提案。野鳥、海、さらには噴火すら島独自の資源として観光プログラムを開発し、地元自然ガイドを養成して、島の人々自身が島の魅力を伝える産業をつくる――野鳥や自然とともに生きる、新しい形のバードアイランドを目指しました。

自然ガイド養成講座のようす

養成講座の卒業生によるガイド
アカコッコやカンムリウミスズメの保護活動は、おもに当会の自然保護部門がにない、島の大切な資源である希少種を守るため、GPSでの行動圏調査や生息地づくりを行ってきました。
そして現在、三宅島は驚異的な森林の回復とともに、地元自然ガイドの活躍でエコツーリズムが産業として定着しつつあります。しかし一方で、移入種のイタチがアカコッコを捕食してしまう長年の問題は解決しておらず、サンゴの白化をもたらす気候変動に加え、近海での洋上風力発電所建設計画など島の自然を脅かしかねない新たな懸念も生まれています。

移入種のイタチ
農作物を荒らすネズミ対策で移入されたが、
アカコッコの天敵に

白化したと富賀浜(とがはま)のサンゴ
2024年9月、海水温の上昇が原因とみられる
サンゴの白化を広範囲で確認
地域の自然を守るには、多くの時間と、人々の理解、協力が必要になります。
30年にわたりレンジャーが常駐してともに生活しているからこそ、三宅島の人々の声にこたえつつ、自然と共生する地域社会を模索することができるのです。
当会は、レンジャーと自然保護部門の連携によって引き続き三宅島の自然を守り、このような人と自然が共生する社会の試みが拡がっていくことをめざしていきます。どうかご支援をお願いします。
野鳥と人が共生する社会を拡げていくために
日本野鳥の会の活動にご支援をお願いいたします


ご寄付のお礼に特製シルバーブローチをプレゼント中!
その他、オリジナルグッズもございます。


オーガニック風呂敷 バードメイトピンバッジ
※プレゼントをご希望の方は、「プレゼントグッズ付き寄付」をお選びください。
島で活動する人たち
島の人々とともに三宅島の自然を守る

三宅島の自然を守っていくためには、その宝である自然が生み出す経済的な還元も重要になってきます。これがなければ、島にとって宝としての自然の価値は小さくなり、不要な開発を招くことにもなります。そのため、島の自然を求めて訪れた方が、滞在日数を延ばし、島でお金を使っていってくれる観光の仕組み作りが欠かせません。
(日本野鳥の会 チーフレンジャー 内藤明紀)
三宅島らしいやり方で三宅島だからこその魅力を伝える

三宅島で陸と海の自然ガイドをやっている菊地ひとみです。
現在活動している自然ガイドはレンジャーたちによって育成された自然ガイド養成講座の修了生です。私たちはここから始まり、環境保全活動、次世代の子どもたちへの環境教育、島の魅力の発掘と発信をやり続けて早や18年。
これからもレンジャーとともに島の人々や自然に寄り添った三宅島らしいやり方で三宅島だからこその魅力を伝え活かしていきたいと思います。
(earth wind & 代表、東京都自然ガイド 菊地ひとみさん)
三宅島で観察できる鳥

アカコッコ
(絶滅危惧ⅠB類)

カンムリウミスズメ
(絶滅危惧Ⅱ類)
(写真:鈴木義晴)

タネコマドリ
(絶滅危惧Ⅱ類)

ウチヤマセンニュウ
(絶滅危惧ⅠB類)

イイジマムシクイ
(絶滅危惧Ⅱ類)

オーストンヤマガラ
(絶滅危惧ⅠB類)
他、モスケミソサザイ(絶滅危惧ⅠB類)、カラスバトなど、約300種の野鳥が確認されている。
森林の回復経過
椎取(しいとり)神社周辺のようす

噴火前
社殿を取り囲む森

2003年1月
火山泥流にのまれた社殿と鳥居のあと

2011年7月
埋没した神社の周辺に緑が戻りはじめる
胴吹きによる森の再生(2019年)

(写真:沖山勝彦)
火山ガスの影響で落葉した樹木の幹から新たに芽が出る「胴吹き」により森は再生
日本野鳥の会の取り組み
当会が独自に行っているアカコッコの保護事業
三宅島はアカコッコの重要な生息地の一つですが、人が放したイタチや噴火、離農による生息環境の変化が影響し、アカコッコは大きく数を減らしました。当会はアカコッコ館の事業に加えて、独自の保護事業を進めています。毎年、島の人々の協力を得て実施している総個体数調査のほか、GPSロガーをアカコッコにつけて1年間の行動を追跡したり、カラーリングを装着し繁殖期の行動範囲を明らかにしました。

アカコッコの背中に重さ1.4gのGPSロガーを装着

GPSの記録をたどって生息環境を確認
こうして蓄積したデータを生息環境の改善にも役立ており、2020年には当会からの提案によってアカコッコは国内希少野生動植物種に指定されました。国への働きかけや、地元や行政、研究者とも連携をしながら保護活動を着実に進めていきます。
アカコッコの森づくり

林床のつる植物を除去する作業
アカコッコ館では、毎年当会の自然保護部門と共同でアカコッコが好む環境を作る「アカコッコの森づくり」を実施しています。
この活動は、島内外のボランティアの方々の協力を得ながら行っており、地面をおおうつる植物を抜いたり水場を設置することで、アカコッコがエサを捕りやすく住みやすくなるよう環境を整備しています。
豊かな海を守る活動

サンゴの生息調査
アカコッコ館が開館した1993年以降、当会のレンジャーは鳥類だけでなく、サンゴの調査や潮だまりでの海水魚の調査を継続して行っています。
そこで蓄積した情報は観察会や環境教育で活用し、海の生きものの魅力や大切さを伝えてきました。2024年度、この活動が日本サンゴ礁学会 保全・教育普及奨励賞を受賞しました。
三宅島
東京から南に約180km、直径約8km、周囲38.3kmの火山島で人口約2200人
三宅島自然ふれあいセンター・アカコッコ館

三宅村村営施設。日本野鳥の会のレンジャーが常駐し、
自然情報の提供、自然観察会の開催、調査・研究などの活動を行っている
野鳥と人が共生する社会を拡げていくために
日本野鳥の会の活動にご支援をお願いいたします

森の魅力を解説するレンジャー

海の自然を伝えるのもレンジャーの仕事
※プレゼント付き寄付について
日本野鳥の会のプレゼント付き寄付は、自然を守る活動に楽しく参加していただく寄付のしくみです。
寄付の金額により、ご希望に応じて野鳥グッズをプレゼントしています。プレゼントが不要の寄付もお選びいただけます。
皆さまのご寄付は、バードアイランド三宅島の野鳥や自然を守る活動や、野鳥と人が共生する社会を拡げていくための活動の資金になります。シマフクロウ、タンチョウ、チュウヒなど絶滅危惧種の保護活動のほか、身近な野鳥たちの調査研究、野鳥と自然の大切さの普及啓発活動などにも使われます。