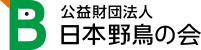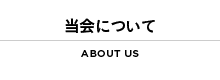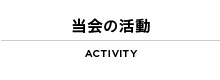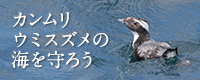トップメッセージ
2026年1月9日 更新
日本野鳥の会 会長 上田恵介
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます!2026年の新春にあたり、日本野鳥の会の会員、サポーターの皆さまに新年のご挨拶を申しあげます。
皆さま、昨年も大きなご支援をありがとうございました。
日本野鳥の会 東北ブロック会議に参加して
私は年末に秋田の大潟村で開催された東北ブロックの総会に参加してきました。地元で子どもたちを集めて自然観察会を開いている元小学校校長の酒井 浩さんによる基調講演がありました。この講演で酒井さんは私たちの活動にも活かせるさまざまな経験を紹介され、とても充実した内容でした。わたしはそのあと鳥の一夫一妻についての話をさせていただきました(が、教科書的であまりおもしろくなかったかなと反省しております)。そのあと自然保護室の浦主任研究員が風力発電の問題についてわかりやすい解説を、普及室の箱田室長代理が最近の本部の活動を紹介しました。
2025年、大きな問題になったクマについては、東北の各支部がそれぞれの探鳥会運営の経験を持ち寄り、対策について話し合われました。クマが身近な存在である東北地方の支部ですから、支部によりクマにどう対処するかについて、さまざまな意見が出され、活発な議論が行われました。夜の懇親会では、毎年恒例の会員出品のオークションが開催され、大いに盛り上がりました。
1000羽のハクガンが舞う空

大潟村での探鳥会のようす
次の朝、エキスカーションでハクガンを見に行きました。マイクロバスが止まると、数百メートル先の水田で採食しているハクガンの群れがいました。1000羽近い大きな群れです。かつては東京湾をはじめ、関東各地に飛来していたハクガンですが、明治期以降、おそらく強い狩猟圧によって、日本への飛来はほぼゼロになってしまった歴史をもっています。それがここまで回復したのは、「日本雁を保護する会」の皆さんの献身的な活動があったからです。なかでも呉地正行さんはハクガンとシジュウカラガンの日本への渡来を復活させるために、アメリカ、ロシアの研究者と共同で、前代未聞のガン復活プロジェクトを成功させたのです。

風車をバックにしたハクガン
ハクガンのプロジェクトは、繁殖地で採取したハクガンの卵を日本に渡ってくるマガンの繁殖地に運び、マガンに抱かせて孵化したヒナたちが、“仮親”であるマガンたちに導かれて日本にやって来ることを目的としたプロジェクトでした。それがこんなに成功するとは呉地さん自身も思っていなかったそうです。
現在、日本で越冬するハクガンは2000羽以上に達しています。まさか日本の空にハクガンたちが戻る日が来るとは……。大潟村で1000羽のハクガンが空に舞っているのを見たとき、ガン類が狩猟鳥であった時代を知っている私にとって、まさに夢をみているような光景でした。

ハクガンの群れ
「ネイチャーポジティブ」への実現に向けて
しかし、いま世界では戦争や熱帯雨林の破壊、さらに温暖化にともなう大きな気候変動が生きものたちのすみかを奪い、生物多様性はかつてない危機にあります。この流れをなんとかくいとめ、2030年までに生物多様性を回復軌道にのせよう、そうした世界的な目標「ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、日本野鳥の会も、国内の数多くの自然保護NPOや国際機関と共同して活動しています。2030年まで、もうあと4年です。
私たちは、シマフクロウやタンチョウの野鳥保護区の整備や、チュウヒ、シマアオジ、アカコッコ、カンムリウミスズメなどの絶滅危惧種の保護を進めながら、海洋プラスチックごみの問題や、風力、太陽光といった自然エネルギーのあり方にも、野鳥保護の視点から意見を発信して、真っ向から取り組んでいきます。
自然を守るには、たくさんの仲間の力が必要です。「野鳥も人も地球のなかま」を合言葉に、2026年も皆さまと一緒に、野鳥のすむ豊かな日本の自然を未来へつないでいきましょう。どうか、今年もお力をお貸しください。ご支援、ご参加をよろしくお願いいたします。
日本野鳥の会 理事長 遠藤孝一
市町村の条例で自然豊かな里地里山を守る
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、新年のご挨拶から始めながら話は昨年末に戻りますこと、お許しください。
人と自然との共生へ向けた新たな一歩
私の住む栃木県市貝町には、サシバがすむ豊かな里地里山を守り、活かしながら、人と自然が共生するまちづくりを進めることを目的にした「市貝町サシバの里保全創造条例」があります(2024年4月1日施行)。この条例は、①保全地域の指定、②里地里山の利用促進、③希少な野生動植物の保護、という3つの柱で構成されています。
昨年12月、この条例にもとづき、私が運営に関わっている「サシバの里自然学校」の活動エリアの中心部、約6.5ヘクタールが、第1号となる「重要里地里山保全地域」に指定されました。

条例で保全地に指定された谷津田と山林
この地域は、細長く続く谷津田とその周囲の山林からなり、サシバをはじめとしてミナミメダカ(レッドリスト:絶滅危惧Ⅱ類)やオオムラサキ(同:準絶滅危惧)、キンラン(同:絶滅危惧Ⅱ類)などの希少な野生動植物の重要な生息・生育地となっています。これまで適度な利用(農林業や自然学校)と適切な環境管理が行われ、良好な生態系が保たれてきたことが評価され、今回の指定に至りました。

保全地に生息するミナミメダカ(絶滅危惧Ⅱ類)

全地に生息するオオムラサキ(準絶滅危惧)

保全地に生育するキンラン(絶滅危惧Ⅱ類)
指定後は、宅地造成や建築、土砂の採取などの開発行為を行う際には町長の許可が必要となり、里地里山の保全がより確実なものとなりました。なお地権者の方には一定の規制がかかる一方で、保全区域内の土地については、固定資産税相当額が奨励金として支払われます。
また、保全区域内では希少な野生動植物の生息・生育環境の維持・改善を図るために、保全計画にもとづいた環境管理活動を推進します。例えば、水田周辺の草刈り、森林内の草刈りと除伐、土水路の維持管理、必要に応じた外来種の駆除などです。サシバの里自然学校がそれを担いますが、町長から「里地里山保全団体」として任命されると、管理活動に必要な経費の助成を受けることができます。

土水路の維持管理作業(法面の草の刈払い)
今後も、農林業の営みによって育まれてきた市貝町の美しい景観や生態系、そして地域文化を次世代へ引き継ぎ、自然と調和した住みよい郷土づくりを進めるために、この条例にもとづく保全地域がさらに広がっていくことを期待しています。
日本野鳥の会ビジョン2030
日本野鳥の会では、2030年を目標に、①絶滅危惧種の保護と野鳥の生息地保全、②地域の自然が地域の手で守られる社会の実現、③生きものや自然に配慮したエネルギーシフト、④自然への理解者の増加、⑤自然保護を担う次世代の育成、という5つのビジョンを掲げています。今回紹介した市町村の条例での取組みが、②「地域の自然が地域の手で守られる社会」の実現につながる事例として、皆さんのお役に立てれば幸いです。
これからも当会は、地域の支部や野鳥保護団体、行政、そして地域の皆さんと力を合わせ、人と自然がともに生きる社会づくりに取り組んでまいります。
本年も、変わらぬご支援をどうぞよろしくお願いいたします。