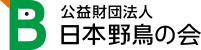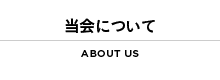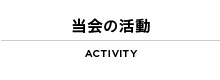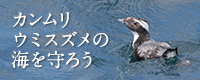トップメッセージ
2025年7月1日 更新
日本野鳥の会 会長 上田恵介
大阪湾でシギ・チドリを見ていた頃
その昔、大和川、淀川、神崎川、武庫川と多くの河川が流れこんでいた大阪湾にはヨシの生える後背湿地をもった広大な干潟が広がっていた。こうした干潟は江戸時代からの新田開発によって、どんどん縮小していったが、大和川の河口干潟の住吉浦は最後まで残っていた。榎本佳樹や小林桂助が鳥の観察や鳥類標本の採集に通っていた、大阪におけるシギ・チドリ観察のメッカであった。
片道30キロ、自転車でシギ・チドリ観察へ
私が干潟のシギ・チドリの観察を始めたのは、高校2年生の時である。鳥好きの高校生3人組(平松君と木村君と私)は、日本野鳥の会大阪支部で知り合った西村さんに誘われて大阪湾の神崎川河口湿地にシギ・チドリを見に通った。西村さんは私たちより二年先輩だった。高校を卒業して、何をされていたのかは知らないが、私たち同様、高校の時の仲間2人(林さんと熊谷さんだったと思う)と3人組で、鳥を見ることに情熱を傾けている変なお兄さんだった。
私は自宅のあった寝屋川から片道30キロの道乗りを、朝早くから自転車をこいで淀川の堤防上を走って、鳥を見に中島町へ通ったものである(若い時は体力あったなあ!)。中島町に初めて行った時にウズラシギを見たこと、アカエリヒレアシシギが意外と小さいなということを知ったこと、それとなぜか海岸部なのにタマシギの巣があったことをよく覚えている。

シギ・チドリの観察に夢中になった高校時代。左から2番目が上田会長
大阪湾のゴミ処分場がフィールドに
高度経済成長の時代、大阪湾では埋め立てがどんどん進行し、その過程で干潟が造成されてシギ・チドリがたくさん来ているらしいというので、大阪南港へ足を伸ばした。さすがに自転車では遠すぎるので、梅田から地下鉄四つ橋線で玉出まで行き、そこからバスで住吉の消防署前まで行き、さらに炎天下、延々1km近い道を歩いて観察ポイントまでいくのである。
その頃の大阪南港は大阪市のゴミ処分場であった。分別なしで、生ゴミもプラスチックも一緒くたに海辺に積み上げられ、腐臭が漂っていた。私たちはゴミの匂いに包まれた8月のかんかん照りの埋め立て地で、干潟に足を取られて泥だらけになりながら、鳥を見ていたのである。泥んこの長靴は、バス停の前にあった住吉消防署で、水道を貸してもらって洗って帰っていたが、地下鉄の車内で、長靴を履いた一行は、絶対、奇異の目で見られていたと思う。
南港はシギ・チドリの渡来時期に限らず、私たちのフィールドになった。我ら3人と西村さん、そして大阪支部の有田さん、塩田さん、辻田さんら常連の7人は、“南港7人のサムライ”と呼ばれていた。

長靴を脱ぎ、ホッと一息
当時のシギ・チドリたち
ハマシギやトウネンの1000羽を超える群れや、ホウロクシギやダイシャクシギなど大型のシギもいた。アメリカウズラシギ、ヒバリシギ、キリアイ、オジロトウネンなど、識別のむずかしいシギたちの識別法もここで覚えた。セグロアジサシやハシブトアジサシを見つけたこともあった。冬はコミミズクを見によく通ったものである。
ある日南港に行くと、2羽のセイタカシギがいた。初めて見たセイタカシギだったが、飛んだところを写真に収めることができた。この記録は写真とともに、『野鳥』誌に報告した。後で考えると、この雌雄のセイタカシギはもしかしたら南港で繁殖していたのかもしれない。
もう一つ、シギの中で私が一番印象に残っているのはコシャクシギである。一人で南港に出かけ、チュウシャクシギがよく降りている草原を歩いていたとき、6羽のコシャクシギが降りているのに遭遇した。コシャクシギはかなりの珍鳥であるし、私にとっても初めての鳥であった。それが6羽もいる!感動の一瞬であった。私はこの時以来、コシャクシギを見ていない。

南港で初めて見たセイタカシギ
干潟消滅の危機、「南港の野鳥を守る会」を結成
そんな中、南港はどんどん埋め立てが進み、シギ・チドリの集まる干潟は海側へと後退して、消滅の危機にさらされていた。観察が一段落して、皆で弁当を食べている時、西村さんが「守る会を作ろうか」と話しはじめた。西村さんは干潟を守ることの大切さを、8月の南港の暑さよりも熱い情熱をもって語ってくれた。
この時代、野鳥の会の支部はまだまだ“趣味の会”の域を出ず、「自然保護」運動をするのには抵抗を示す人たちも多かったのである。だから別の会を作ろうということになって、「南港の野鳥を守る会」の結成が決まった。1968年のことである。会には酒井さん夫妻が加わり、酒井健さんが会の事務局長的な役割を引き受け、会長には当時、靱(うつぼ)公園にあった大阪市立科学博物館の館長の筒井嘉隆先生(SF作家の筒井康隆のお父さん)に来てもらうことになった。
守る会の事務所は箕面市瀬川の酒井さん夫妻のお宅に置かせてもらったので、酒井さん宅は私たちグループのたまり場になり、毎週、若い会員たちが集まっては活動について話し合っていた。
会の活動方針は、当時東京湾の干潟の保護運動をしていた蓮尾順子さんら“新浜3人娘”が活躍していた「新浜を守る会」、そして私と同じ年の花輪伸一さんらが活動していた仙台の「蒲生干潟を守る会」の活動を参考にさせてもらった。とりあえず南港のシギ・チドリの絵葉書を作って販売して活動資金を稼ぎ、署名運動をして、それを大阪市に届けようという“割と安易な”活動方針が決まった。
署名は野鳥の会の会員、その家族や友人、さらには休みの日には大阪駅前に皆で署名版を持って立ち、道行く市民から署名を集めた。そして最終的には8400名の署名が集まった。

大阪駅前での署名活動のようす。後ろは阪神百貨店
当時の大阪市長は中馬馨氏、助役(副市長)が大島靖氏であった。実は大島氏は筒井先生の三高(京大)時代の後輩であったことから、私たちは筒井先生とともに署名をたずさえて大阪市役所を訪ね、助役室で大島氏に野鳥公園設置について話を聞いてもらった。
南港野鳥園設置の署名はすぐに市長に届けられ、中馬氏はその年の2期目の市長選に野鳥園の実現を選挙公約に掲げて再選されたのである。1971年のことであった。
南港野鳥園の実現にはいろいろ苦労もあったが、後で振り返ってみると割と簡単に決まったようにも思う。若いメンバーの活躍は大きかったが、酒井夫妻、筒井先生の人脈や当時の社会情勢によるところも大きかったのだと思う。ラッキーであった!
日本野鳥の会 理事長 遠藤孝一
ヒヨドリの思い出
庭などの身近な場所から、森林までいろいろな環境で見られるヒヨドリ。色合いが地味なことから、探鳥会での人気はいま一つですが、私にとっては思い出深い野鳥です。
野鳥への興味
時は五十数年前。私が中学生だった時にさかのぼります。そのころ私は、友人と悪ふざけをして足の骨を折り、一時的に激しい運動ができず、時間と体力をもてあましていました。そんな時、新聞で「冬は野鳥にとってエサが少なくつらい季節。冬は都会にも山や北国から野鳥がやってくる。餌台を作ると、野鳥も助かるし、身近で観察もできて楽しい」という記事を見つけました。
私は子どものころから生きものが大好きで、幼稚園の時の愛読書は図鑑。それを見ながら、アフリカのサバンナを走り回るシマウマやキリン、それを襲うライオンにあこがれました。小学生の時はずっとクラスの生きもの係で、家ではブンチョウやセキセイインコなども飼っていました。一方で野鳥への興味はまったくなく、存在さえも気づいていなかったかもしれません。それが突然、この記事を見て、野鳥への興味が湧き出したのです。
「謎の鳥」との出会い
私の生家は東京都文京区。我が家には庭はありませんでしたが、幸いにも隣の家には庭がありました。そこで、隣の家に近いベランダに餌台を作り、パンくずを置いてみました。しかし、来たのはスズメだけ。ところが餌台には来ませんが、スズメとは違う鳥が隣の庭にいることに気がつきました。
その「謎の鳥」は、遠くから肉眼で見た感じでは(その時は、当然ながら双眼鏡は持っていませんでした)色は黒っぽくて、大きさはハトくらい。野鳥図鑑を引っ張り出して調べてみましたが、当てはまる野鳥はいません。もっと近くから見るしかないと思って塀越しに庭をのぞくと、そこにいた野鳥は、黒ではなく灰色の体をしたヒヨドリでした。

秋冬は柿を食べている姿もよく見かける
この記念すべき野鳥の識別初体験以来、不思議と野鳥が目に付くようになりました。以前、当会から出版していた『窓をあけたらキミがいる』という初心者向けのバードウォッチングの本の中に、「心の窓を開くと、身の回りに意外と多くの野鳥がいることに気づく」と記されていましたが、まさにその通り。それまで、野生味あふれる生きものは、遠いアフリカのサバンナや熱帯のジャングルにしかいないと思っていたのですが、身近なところにいるではありませんか。そして当会に入会して探鳥会に通うようになり、さらに野鳥にはまり、いまにいたっています。

当会の探鳥会に通って、より野鳥が好きになった
ということで、バードウォッチャーにはあまり人気がない?ヒヨドリですが、私にとっては運命的な出会いをもたらしてくれた思い出深い野鳥なのです。